どうも、39歳・白帯1ヶ月半、ハゲたけど黒帯を目指す会社員です。
今日は僕の中でちょっとした「事件」がありました。
これまで僕の得意技(というか、逃げ道?)は**「引き込み」**でした。
そう、立ち技で組み合った瞬間に「えいやっ」と尻もちついて下から展開する、あのやつです。
初心者にとって引き込みは安心感の塊。相手の力強いタックルや投げに付き合う必要がないし、自分の土俵(下のポジション)で戦える。
ところが――この日、その僕の唯一の得意技が完全に封じられたのです。
引き込みが通じない!? 白帯の動揺
いつものように格上の先輩とスパーリング。
「よし、ここは引き込んで下から狙っていこう」――そう思った瞬間、相手はスッと腰を引いて距離を取り、僕の動きを完璧に読んでいました。
「え、なにそれ。僕の十八番、無効化ですか?」
その後も何度か挑戦しましたが、結果は同じ。まるで相手の重心が揺るがない。引き込みに入る隙を与えてくれないのです。
そして数分後。
結果、僕は――
腕を4回折られました。
いや、もちろん実際に折れたら救急車です(笑)。
でもそれぐらい極められた。
腕十字やら肩固めやら、気づけば僕の腕が“バキッ”といきそうな角度に。タップしては、また同じ流れ。
心の中で「今日だけで寿命10年縮んだんじゃ?」と思ったほどです。
「崩し」とは何か? 初めての本気対話
スパー後、僕は汗だくでマットに寝転びながら、頭の中で一つの言葉がグルグル回っていました。
「崩し」。
柔術の先生や先輩がよく口にする言葉です。
「相手のバランスを崩せ」
「崩しがなければ技は入らない」
正直、これまでの僕はその言葉をどこかスルーしてました。
「いやいや、崩すとかより、まず形に入るのが大事でしょ?」くらいの軽い感覚。
でも今回の体験で思い知らされました。
崩せなければ、すべての動きが封じられる。
引き込みも、スイープも、サブミッションも。
相手の重心がどっしりと安定していたら、何も始まらないんですよね。
無理に突破しようとすると、逆に相手に優位な体制を取られたりします。
崩し=相手の心と体を「ズラす」こと
では「崩し」って実際何を意味するのか。
初心者なりに考えてみました。
- 重心をズラす
相手の腰や足をコントロールして、バランスを取れない状態にする。 - 意識をズラす
相手に「こっちを警戒しろ」と思わせて、別方向に仕掛ける。 - 呼吸をズラす
相手が吸った瞬間に圧をかける、緩んだ瞬間に仕掛ける。
結局のところ「ズラす」ことが崩しなんじゃないか、と。
つまり「正面からぶつかって勝負」じゃなくて「ちょっと揺さぶって隙を作る」。
柔術って、やっぱり頭脳戦なんだと改めて感じました。
まとめ:崩しを学ぶのは「人生そのもの」
今回、引き込みを防がれて「僕の土俵」がゼロにされました。
その結果、何度も腕を折られ(そうになり)、崩しの大切さを身にしみて理解しました。
柔術って不思議で、練習すればするほど「技術」以上に「考え方」を突きつけられるんですよね。
相手を崩すには、まず自分の固定観念を崩さなきゃいけない。
同じ動きに固執していたら、すぐに詰む。
これはもう、人生そのものじゃないですか。
これからの練習は「崩し」をテーマに、自分の柔術を少しずつアップデートしていきたいと思います。
そしてまた、格上の先輩に挑んで――腕を5回、6回と折られながら(笑)、成長していくつもりです。
☟合わせて読みたい記事☟


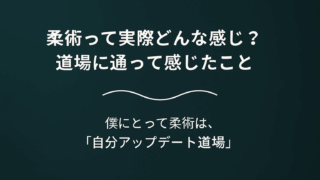
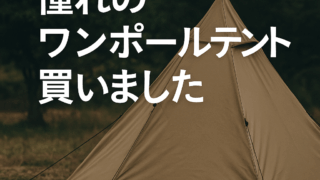



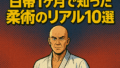

コメント